体験Activity
天平ろまん館では、「砂金採り体験」や「天然石探し」ロマンを感じられるワクワクする体験ができます。

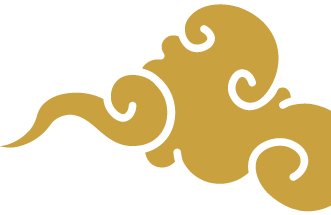

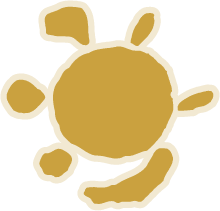

聖武天皇の御代、天平21(749)年。陸奥国は、現在の宮城県涌谷町(箟岳丘陵)から産出した黄金900両(約13kg)を、奈良の都に献上しました。国内初産出となったこの黄金は、国家事業であった東大寺大仏を完成へと導きました。
天平ろまん館は、産金の歴史を「学ぶ」こと、砂金採りを「体験する」こと、産金の地で四季を感じながら「安らぐ」ことで、日本古代史上に特筆される「天平産金の地」を体感できる施設です。
天平ろまん館がある「わくや万葉の里」には、国史跡「黄金山産金遺跡」があります。令和元年度、「みちのくGOLD浪漫—黄金の国ジパング、産金はじまりの地をたどる−」のストーリーが日本遺産に認定され、「黄金山産金遺跡」は構成文化財の1つとなっています。
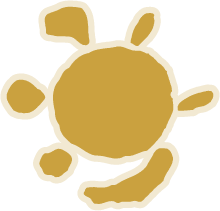
FEATURE
FEATURE
3月17日㈰に涌谷町地域おこし協力隊 「ちいさなふしぎ」さんが プロデュースするイベント「今日はハレる日」が天平ろまん館で開催されます!天平ろまん館開館30周年を記念して天平衣装をはじめとする
FEATURE
天平ろまん館直売所にて、東北弁アレンジの落語で活躍中の六華亭遊花さんをお招きしての寄席、ティーウエリスト仙台校校長として活躍中の岩城礼子さんをお招きしての健康ブレンド茶の試飲と講演会を実施します。笑い
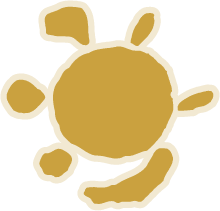
749年に日本で初めて黄金を産出した涌谷町。その黄金は奈良東大寺の大仏を完成に導きました。
天平ろまん館では、ろまん館では産金の歴史や当時の産金技術を砂金採り体験などをしながら学び、遠く1,250年前におきた日本黄金史のキセキを体感できます。